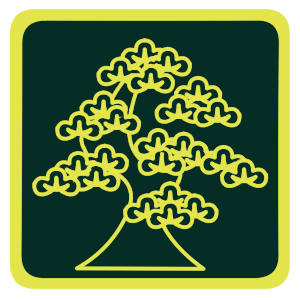解体の危機迫る。実録! 現存天守はいかにして明治時代を乗り切ったか
どうも! 当サイト管理人の犬彦です。
明治時代になって急激にその価値を失い、ボコボコと壊されていった日本の城郭。現存している天守だって、初めから大事にされていたわけではありません。むしろ解体の窮地に立たされ、それを何とかしのいだという苦い経験があるのです。ということでそんなエピソードの数々をご紹介します。
お城を救った陸軍大佐

城郭が時代遅れの遺物と化した明治時代初期、廃城令での破却こそ免れた姫路城でしたが、陸軍が利用しやすいように御殿や三の丸建造物が撤去されてしまいます。また天守が23円50銭という安値で地元商人に売却されるも、使い道がなく放置され、他の残存建造物と共に朽ちるに任せる状態となります。そんな姫路城の窮地を救ったのが陸軍大佐中村重遠でした。彼が姫路城を名古屋城と共に保存すべきと陸軍卿・山縣有朋に訴えたことにより、陸軍の費用での修理が実現。これが後の「明治の大修理」の先鞭となりました。
姫路城
天皇の命で解体免れる

明治の廃城令では一応存続となった彦根城でしたが、まともなメンテナンスもなく朽ちてゆくばかりで、その内800円(当時)で売却され、解体される流れに。しかし1878年、北陸行幸を終えたばかりの明治天皇の命によって一転、保存されることになりました。この経緯には二つの説があります。ひとつは行幸に同行した大隈重信が保存を奏上したという説。もうひとつは浄土真宗福田寺の住持(寺の長)の妻が奏上したという説。ちなみに福田寺の住持は井伊家の血筋の者で、その妻は明治天皇の従妹でした。
彦根城
博覧会で危機脱出

江戸時代には藩政の中心を担った各地の城ですが、明治時代になるとその役割を終え、無用の長物扱いされてしまいます。松本城も例外ではなく、明治五年に天守が競売にかけられ、235両で落札されました。落札者は取り壊す気マンマン。それを憂いた地元の名士、市川量造が天守存続のために動きます。落札者や行政当局に掛け合って、旧本丸の10年間貸与にこぎつけると、松本城を使って博覧会を開きます。これが大当たりで、量造はこの収益を基にして松本城の買戻しに見事成功、何とか取り壊しを防いだのでした。
松本城
藩士と豪農、天守を買う

お城にとって暗黒期ともいえる明治時代初期、松江城でもほとんどの建造物が撤去されました。さらに天守が180円(当時)で払い下げられることに。この値段、正直そこまで高くありません。あれ、これ、何とかなんじゃね? と思ったのが、旧藩士の高城権八という人物でした。彼は知り合いの豪農・勝部本右衛門父子とタッグを組んで資金を調達、天守の買い戻しに成功しました。その後は1890年に旧藩主の松平家に譲渡され、1892年に市民の寄付などで大修理が実現、1927年松江市に寄贈という流れで保存に至っています。
松江城
天守、寺になる

明治6年(1873年)の廃城令によって丸岡城に下った処分は「廃城」。建造物がボコボコと解体され、天守だけがポツンと残る寂しい状態に。その天守も3両2分という破格の安値で民間に払い下げられましたが、有志の買い戻しで何とか解体は免れました。しかしその天守を今後どうするかが当然問題となるわけで。ならばいっそのこと寺にしちゃえば? ということで明治34年に丸岡町に寄付されるまで、長昌庵という寺として使われていました。住職が天守内で時報の太鼓を打っていたのだとか。
丸岡城