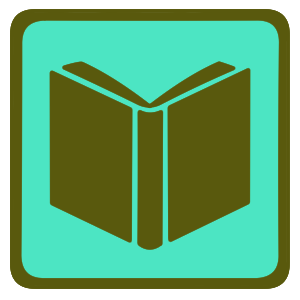国の需要文化財に指定されている天守は7城。その勇姿を目に焼きつけよ!
どうも! 当サイト管理人の犬彦です。
江戸時代から残っている現存天守は全国に12城です。その内国重要文化財に指定されているのは7城。本記事ではその7城は一気に紹介します。ではどうぞ!
松山城

標高132メートルの勝山に建造された平山城ですが、山頂に本丸、山麓に二之丸・三之丸を配し、山城を思わせるような縄張りになっています。「賤ケ岳の七本槍」のひとりとして知られている加藤嘉明によって、1602年に築城が開始。城郭は加藤家から蒲生家、そして久松松平家へと引き継がれていきました。火災の被害に遭うことが多く、大天守も一度焼失していますが、1854年に再建されたものが現存しています。大天守など21棟が国重要文化材に指定されています。
愛媛県松山市丸之内1
高知城

関ケ原の合戦後、新たな領主として土佐入りした山内一豊は、南北朝時代から城が存在していた標高42メートルの大高坂山に新たな城を築きました。以降土佐山内家の居城として、藩主を他家に譲ることなく明治まで続きました。現存している建造物は、追手門を除いて1727年の大火以降に再建されたものです。国内で唯一、本丸の建造物が完全に残っている城郭で、復古式として名高い天守の他、懐徳館は国内に二棟しか現存していない本丸御殿として貴重です。15件が国重要文化財に指定されています。
高知県高知市丸の内1-2-1
宇和島城

標高74メートルの丘陵地に古来より存在していた板島丸串城が、藤堂高虎によって本格的な城郭に生まれ変わりました。城主が藤堂高虎から富田信高を経て、伊達政宗の長子・秀宗になると、宇和島城と呼ばれるようになり、以来伊達家の居城として定着します。国重要文化財に指定されている天守は、独立式で小ぶりですが、白壁の長押形や破風の多用など装飾に富んだ美しい建物です。また薬医門としては国内最大級の上り立ち門が城の南側に残っており、市指定有形文化財となっています。
愛媛県宇和島市丸之内
丸亀城

室町時代から砦があった標高66メートルの亀山に、生駒親正・一正父子によって1602年に完成した丸亀城は、一国一城令によって一旦は廃城となります。しかし1642年、山崎家治によって再築が開始。山崎家が断絶した後も京極家が普請を引継ぎ、高石垣が特徴的な平山城を完成させました。明治時代にほとんどの建造物が破却されましたが、天守と大手一の門、大手二の門が現存し、国重要文化財に指定されています。天守と大手門の両方が現存する城郭は、他には高知城と弘前城だけです。
香川県丸亀市一番丁
備中松山城

1240年、秋庭重信が臥牛山に砦を築いたのが始まりとされています。山陰につながる山陽の玄関口でもある備中にあって、北の中国山地と南の瀬戸内海を望む重要拠点として、様々な勢力による攻防が繰り返されてきました。江戸時代になると、小堀政次・政一親子を経て、水谷勝宗の改修によって現在の姿となりました。二重二階と小さいながらも山城で唯一の天守が現存しており、他に本丸二重櫓と三の平櫓東土塀が国重要文化財に指定されています。平成9年に本丸の櫓2棟、門4棟、土塀が復元されました。
岡山県高梁市内山下1
丸岡城

一向一揆平定の恩賞として柴田勝家が織田信長から越前国を与えられると、彼の甥・柴田勝豊は1576年に北ノ庄城の支城となる丸岡城を築きました。天守は古式の望楼型で、現存天守では唯一石瓦が使われています。明治時代に天守以外の建造物はすべて解体されました。天守は太平洋戦争の被害を受けなかったものの、1948年の福井地震によって倒壊してしまいます。それでも1950年に国重要文化財に指定され、1955年に倒壊前の建材をできる限り利用して修復再建されました。
福井県坂井市丸岡町霞1-59
弘前城

1611年、津軽信枚によって築城。江戸時代を通じて津軽家の居城として、また弘前藩政の中心として機能してきました。天守は当初五重でしたが、1627年に焼失。現在の天守は1810年に本丸南東隅櫓を改築したもので、東北地方で唯一現存する天守となっています。天守を含めて9棟の建造物が現存し、すべて国重要文化財に指定されています。また堀、石垣、土塁の残存状態も良好です。かつての城域は弘前公園として活用されており、桜の名所として知られています。
青森県弘前市下白銀1