
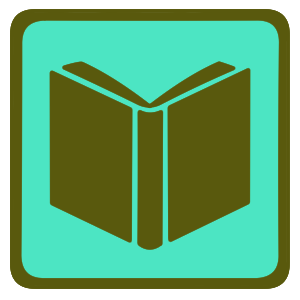
城郭・城下町を舞台にした日本文学をいらすとやと共に巡ってみよう!
どうも! 当サイト管理人の犬彦です。
壮大かつ美しいお城、そしてその城下に住む人々の営みは、文学にとっても恰好の題材となってきました。ということで、フリーイラスト素材の帝王「いらすとや」と共に、お城文学を巡ってみましょう。
姫路城を文学で味わう

お城が舞台となっている文学の代表といえば、やはり『天守物語』でしょう。作者は明治時代の文豪、泉鏡花。舞台作品として数多く上演されているだけでなく、1995年には何と映画化までされている人気戯曲です。内容は、魔物が蠢く怪奇物語と思いきや、大天守に棲む魔性の女、富姫と、鷹匠の若侍、図書之助の純愛物語へと発展していきます。明治文学ということもあって、原文はいささか読みづらいですが、おどろおどろしさとロマンチックが合体した和風ファンタジー、興味があれば是非お試しあれ!
姫路城
文豪が描いた武士の世界

文豪・森鴎外の小説『阿部一族』の元ネタとなったのは、いろいろと現代人には理解しがたい武士の世界でした。熊本藩主・細川忠利が1641年に死去した時、後を追って切腹した者が19人にも登りました。殉死者の遺族は大抵、藩から厚遇されるものですが、殉死者のひとり、阿部弥一右衛門の遺族はなぜか冷遇されます。それにイラッとした長男が忠利の法事で無礼な態度を取って捕まると、弟達はブチ切れて兄の屋敷に立てこもり、討伐隊との激しい戦いの末に全滅しました。長男はその後、縛り首に。何だかなぁ……。
熊本城
文豪の紀行文に描かれる

1927年、東京日々新聞と大阪毎日新聞の紙上で、日本八景が大々的に発表されました。これは日本を代表する山岳・溪谷・瀑布・温泉・湖沼・海岸・河川・平原の風景を選定しようという企画で、さらに当時の人気文士達による日本八景の紀行文が先記二紙上に連載されました。日本八景の河川部門で選ばれたのは、犬山城の傍を流れる木曽川で、その紀行文を担当したのが北原白秋。紀行文の一章目が『白帝城』として有名で、息子と共に訪れた犬山城の壮麗な様が描かれています。
犬山城
文豪、傷心を松江で癒す

国語の教科書でもお馴染の大作家・芥川龍之介は、東京帝国大学在学中の1915年の夏、失恋の傷を癒すべく、友人の招きを受けて松江に約半月滞在しました。この時の経験や思いを『松江印象記』という文章で綴っています。松江城についての記述もありますが、松江城を称えるというよりは、松江城を利用して国内の城や古い芸術品を簡単に破壊してしまう当時の風潮を理屈っぽく批判しているという印象ですね。ちなみに芥川の出世作『羅生門』が発表されるのは、この三か月後のことです。
松江城
松江にゆかりの小泉八雲

松江にゆかりのある人物といえば、やはり小泉八雲(1850-1904)ですよね。出生名はパトリック・ラフカディオ・ハーンで、ギリシャのレフカダ島生まれ。40歳で来日してからはずっと日本で暮らしました。妻・せつと出会った松江には一年ちょっとしかいませんでしたが、この地から受けた印象は深く、作品集『知られぬ日本の面影』の中の一章、『神々の国の首都』で瑞々しく描かれています。松江城天守についてもなかなかユニークな表現で記されています。またお城の人柱伝説についても短く触れられています。
松江城




