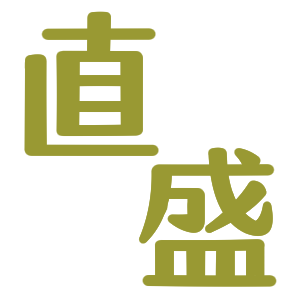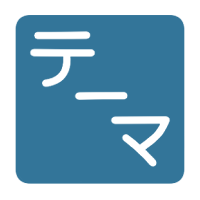
姫路の城は女の城! 華麗な城を彩った美しき個性派姫君を紹介します

どうも! サイト管理人の犬彦です。
日本を代表する城郭といえば姫路城ですよね。現存建築物が非常に多いという史跡的な価値だけでなく、壮大で美しいという芸術的な価値も高く評価されています。そんな姫路城にはかつて、その地名故なのか、強烈なインパクトを放つ姫君が存在していました。今回は姫路お城まつりでお馴染みの三姫プラス一姫をご紹介いたします。
督姫(?―1615)

徳川家康の次女で、母は家康の側室・西郡局。最初の旦那は北条氏直でしたが、氏直との死別後、1594年に豊臣秀吉の仲介で池田輝政と再婚します。 なお、輝政にとっても再婚で、前妻との間に子・利隆がいました。 夫婦仲は良好だったようで、五男二女に恵まれます。 関ケ原の合戦での功績で、輝政が姫路を得ると、姫路城を現在の美しい姿に改修したことは周知の通り。
輝政の死後、利隆が姫路藩を継ぎますが、この経緯にはちょっとした伝承があります。 督姫は自分の子・忠継を藩主にしたいあまりに、利隆を毒饅頭で殺そうとしたというのです。 しかしその場にいた忠継が母の悪だくみに気づき、異母兄を救うために自ら毒饅頭を食らって死亡。 その息子の姿を目の当たりにして、悔恨の念に駆られた督姫も、息子の後を追って毒饅頭を食らって死にました。
この伝承はかなり有名なのですが、史実とは矛盾していますので、後世の作り話です。信じないように。
千姫(1597―1666)

池田家二代藩主・利隆が33歳の若さで病死。嫡男の光政はまだ8歳で、大藩姫路を任せるには若すぎるということで鳥取藩に移り、代わりに桑名藩から本多忠政が姫路入りしました。 この忠政の長男夫婦こそが、イケメンで名高い本多忠刻と、かつて豊臣秀頼の妻だった千姫です。
千姫といえば、二代将軍・徳川秀忠と浅井三姉妹の一人・江との子で、7歳で豊臣秀頼と政略結婚させられ、大坂夏の陣(1615年)の時に救出されたことで有名ですね。 その後は伏見城にしばらく留まってから江戸に帰ることになるのですが、その時立ち寄った桑名で20歳の忠刻と出会い、この時19歳の千姫に恋心が芽生えます。 江戸に帰ってからしばらく経って、次の縁談話になった時、自ら忠刻を推したようです。
桑名から姫路に移ってからは姫路城西の丸に居住していました。 とても仲睦まじい夫婦でしたが、残念ながら幸せな生活は長く続きませんでした。 忠刻が30歳で病死してしまったからです。 以降の千姫はずっと江戸で暮らしていたようです。
高尾太夫
太夫とは遊女の最高位に与えられる称号で、ただ単に美しいだけでなく、芸事に優れ、高い教養を身に付けていなければ務まりませんでした。 さらにその中でも、江戸吉原の三浦屋の大名跡・高尾太夫は、まさに遊女のトップに立つ存在でした。
1732年に姫路藩主となった榊原政岑(1715-1743)は、とにかく遊郭好きで知られ、さんざん豪遊した挙句、1741年に高尾太夫を身請けし、姫路城に連れて帰りました。 身請けにつぎ込んだ額は何と2500両。 さらには身請けの際に3000両で酒宴を開いてドンチャン騒ぎ。 間が悪いことに、当時の将軍は質素倹約を推し進めていた徳川吉宗で、当然ながらブチ切れられます。 これはどういうことだ、と幕府の老中に詰問されると、榊原家の家老が、高尾太夫は政岑の乳母の娘だったので情で身請けした、と苦しい言い訳をしたと言われています。
榊原家は家康時代からの名門ということもあって改易は免れますが、政岑は隠居を命じられ、家督を継いだ息子・政純と共に姫路を追放、越後高田に減封となりました。 高尾太夫も越後高田に移り住み、政岑の死後は江戸に戻り、榊原家の下屋敷で暮らしたとされています。
喜代姫(1818-1868)
酒井家五代藩主・酒井忠学の正室・喜代姫は、十一代将軍・徳川家斉の何と二十五女とされています。
家斉といえば、20人以上の側室を抱え、50人以上の子供を設けるという性豪ぶりが有名で、「オットセイ将軍」とも呼ばれています。 そしてこの多くの子供を、男子は養子として、女子は妻として、大名家に送り込むことによって、徳川家の力はより盤石なものになってゆきました。 もっとも、家斉自身にそんな政治的意図はなかったようですが。
で、忠学と結ばれて、一応は姫路のお姫様となった喜代姫ですが、実はずっと江戸にある酒井家の屋敷で暮らしていました。 江戸幕府が終焉し、時代が明治に変わった直後、混迷する江戸を離れて姫路に向かいますが、その道中、50歳で近江の大津で死去。 結局、姫路に足を踏み入れることは一度もありませんでした。
ちなみに、姫路城に程近い老舗和菓子屋・伊勢屋本店の銘菓「玉椿」は、酒井忠学・喜代姫の婚礼の際に、家老・河合道臣の命によって作られたものです。