テーマネタ

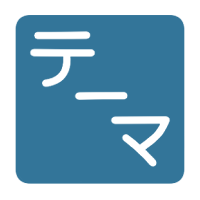
諦めるのはまだ早い! 兄がたくさんいても殿様になれた人物を紹介します
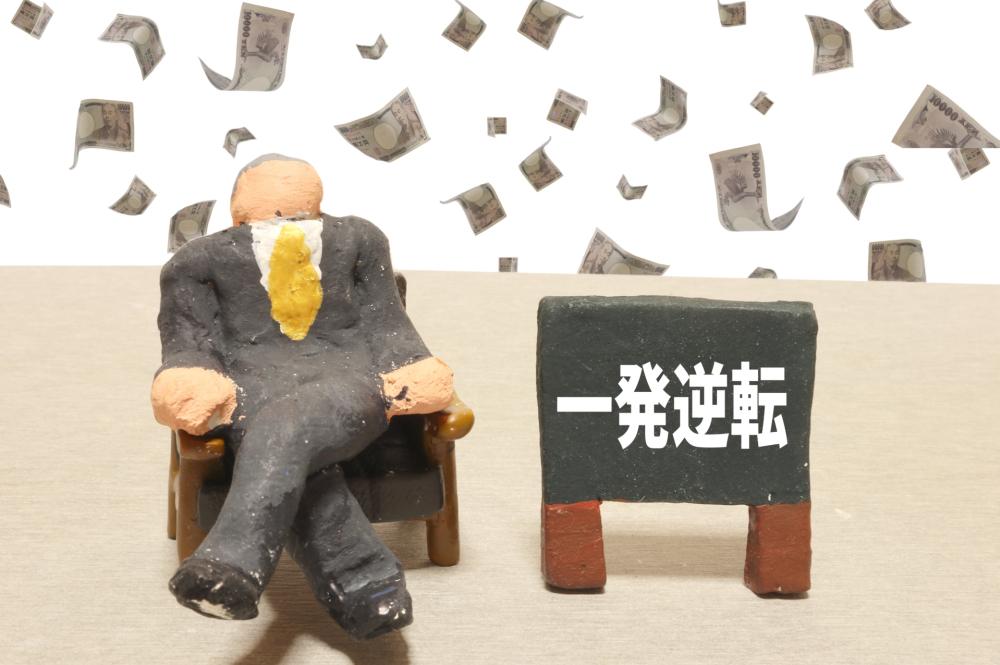
どうも! サイト管理人の犬彦です。
大名家にとって、血統の断絶を防ぐため、子供は多いに越したことがありません。ただし産まれる順番が遅い子ほど、後継者になれる確率が当然低くなり、その分冷遇を受けたりします。それでもノーチャンスではありません。今回は兄がたくさんいても、何だかんだで藩主になれた人物を紹介します。
※ 当記事には一部、小ネタと内容が重なるものがあります。
紀州藩五代・徳川吉宗(1684―1751)

最も有名な末っ子殿様といえば、やはり暴れん坊将軍こと徳川吉宗でしょう。 二代・光貞の四男坊で、世に出ることなく一生を終えてもおかしくない立場でした。 13歳の時、時の将軍・徳川綱吉から越前葛野藩3万石を賜りますが、領国経営は家臣が行い、吉宗は紀州で気ままに暮らしていたようです。
転機は1705年、22歳の時。
長男・父・三男と次々に死亡。 次男もすでにこの世におらず、藩主の座が吉宗に転がり込んできました。 このあまりの急展開に、吉宗が兄達を謀殺したのでは、という噂が囁かれることに。
