テーマネタ

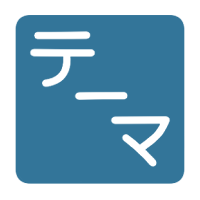
坂崎直盛。激動の時代をただ真っ直ぐに突っ走ったメンドイ武将の物語

どうも! サイト管理人の犬彦です。
幾多の戦場を駆け巡り、常に生死の境を渡り歩いてきた戦国武将には、大抵強いクセやアクがあるものです。そうでなければ生き残れないですからね。今回紹介する坂崎直盛(1563-1616)は、その最たる例と言っても良いでしょう。正直なところ、この人、相当メンドイです。
第一章|キリスト教を巡って暴走する
「戦国の梟雄」として知られる備前の有力武将・宇喜多直家には、忠家という弟がおり、坂崎直盛はその子です。 つまり豊臣政権下の五大老・宇喜多秀家のいとこに当たります。 もっとも坂崎姓を名乗るのは関ケ原の合戦以降で、それ以前は宇喜多詮家とか浮田左京亮とか呼ばれていたようです。 本記事では、坂崎改姓までは左京亮とします。
左京亮は24歳の時、大阪城下で聴いたキリシタンの講話にいたく感動し、さらに後日、ヴィセンテの洗礼名を持つ日本人修道士と議論したことでキリスト教に完全に陶酔、すぐに洗礼を受けさせろと要求します。 ヴィセンテは、もっとたくさんの教理を理解しないととダメだ、と諭しますが、キリスト教への情熱が沸点に達していた左京亮は、それならすぐに教理を教えろ、と強情に迫りました。 ヴィセンテは仕方なく、左京亮に必要な教理を突貫で教えて洗礼を授けました。
この時点ですでにメンドイです。
この頃、豊臣秀吉によってバテレン追放令が出されており、表立ってキリスト教の活動をすることが危険な状態になっていました。 ヴィセンテは左京亮に、宇喜多家の安全のためにも入信を秘密にするようにと説得し、左京亮も一旦は了承します。 が、本国・備前に戻るとヴィセンテとの約束をあっさり破り、周囲に自身の入信をベラベラ喋り、さらに布教じみたことまで始める始末。
約束はちゃんと守りましょう。
