テーマネタ

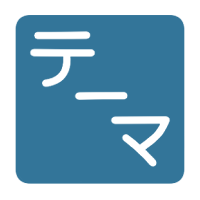
武士の心は抹茶風味? 茶道を愛し、茶道に愛された茶人殿様をご紹介

どうも! サイト管理人の犬彦です。
最もポピュラーな武士の趣味といえば、やっぱり茶道。茶室はいわば武士同士の交流・社交の場でもあり、茶道の作法は武士が身に付けるべきたしなみ・マナーでもありました。今回は、そんな茶道の世界にどっぷりはまったお殿様をご紹介します。
松江藩主 松平不昧(1751―1818)

松江のお殿様といえば、やはり不昧の茶号を持つ松平治郷ですよね。 借金まみれのボロボロ藩を、国内屈指の豊かな藩へと変貌させた政治手腕は見事でした。 また彼は自らの流派を持つほどの重度の茶道マニアでした。 好転した藩財を武器に、他家が手放した茶道名器をバンバン買い取り、雲州名物と呼ばれる一大コレクションを作り上げました。 さらに蒐集品を七段階にランク付けして分類し「雲州蔵帳」というコレクション帳に記載。 その上で自ら定期的に状態をチェックし、手入れし、時には修理までしました。まさにマニアの鑑です。
