テーマネタ

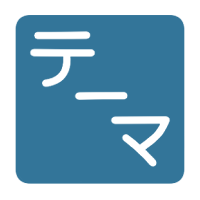
お国入りしたものの跡取りができなくて一代で改易となった大名家をご紹介

どうも! サイト管理人の犬彦です。
官職や身分、領地を取り上げることを改易と言います。殿様の乱心とか、家臣同士のいざこざとか、その理由は様々ですが、跡取りがいない、というのが江戸時代では一番多かったりします。今回は無嗣断絶により一代限りで改易となった、トホホな大名家と、それにまつわる逸話や伝説をご紹介します。
岡山藩主 小早川秀秋(1582―1602)

関ケ原の合戦以来、裏切者の代名詞となった小早川秀秋。 実は豊臣秀吉の正室の甥で、秀吉の後継者候補として大事にされていた時期がありました。 それが秀頼の誕生で一転、用無し扱いされ、毛利家の家臣・小早川家へ養子に出されることに。 そりゃあ豊臣家を裏切りたくもなりますよ。 関ケ原での裏切りで彼が得たものは、彼に裏切られた側の武将のひとり、宇喜多秀家の領地でした。 おそらく複雑な思いで領地入りしたでしょうが、子も作らずにたった2年で死去。 どうやら酒浸りだったようで、アルコールが原因と考えられています。
松山藩主 蒲生忠知(1604―1634)

会津藩を領有していた蒲生家でしたが、跡取りがいないまま二代・忠郷が死去。 弟の忠知への家督相続が認められますが、1627年に伊予松山藩に転封となりました。 しかし忠知にも跡取りができませんでした。 その焦りからか、忠知は次第に精神を病んでゆき、自身の屋敷の前を妊婦が通るたびに捕まえて殺害し、さらにその腹を切り裂いて胎児を引きずり出すようになった、という話が伝わっています。 もっとも信用に足る話ではありませんが。 結局、松山入りから7年で忠知は死去、蒲生家は改易となりました。
