
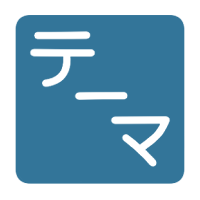
城が欲しけりゃ俺に任せろ! 多くの名城を生み出した築城名人をご紹介

どうも! サイト管理人の犬彦です。
戦国大名、戦いに強いだけではダメです。敵が領国に攻め寄せてきた時の防御、つまりはお城がちゃんと造れない人には務まりません。ということで、今回はお城造りに抜群のセンスを発揮した築城名人を3名ご紹介します。
藤堂高虎(1556~1630)

築城名人といえば、まずはこの人ですよね。
近江生まれ。初めての主君・浅井長政が織田信長に倒されると、主君を転々と変えます。 その後に仕えた羽柴(豊臣)秀長とは相性が良く、功績を挙げまくってドンドン出世。 秀長の死後は子の秀保に仕え、秀保の死後は秀長の兄・秀吉に仕え、大名にまで登りつめます。 しかし秀吉より徳川家康との方が相性が良く、秀吉の死後、迷うことなく家康側につきます。 関ケ原の合戦や大坂の陣で活躍し、家康死後も徳川家に尽力し続けました。
お城造りの実績として、和歌山城(1585年|羽柴秀長の下で普請奉行)、宇和島城(1596年|板島丸串城跡に新築)、今治城(1602年|新築)、伊賀上野城(1611年|大改修)、津城(1611年|大改修)、膳所城・篠山城・亀山城(天下普請の縄張りを担当)などがあります。
黒田孝高(1546~1604)

官兵衛や如水の名でも知られ、戦国史に燦然と輝く名軍師も築城名人でした。
播磨生まれ。地元の武将・小寺政職の下で、若い頃から軍才を発揮。その後、頭角を表してきた織田信長に臣従。 信長の家臣だった羽柴(豊臣)秀吉と行動を共にするようになり、その優れた知略で秀吉の天下取りに多大な貢献を果たします。 九州平定の功により、豊前六郡を拝領。 秀吉の死後、嫡男・黒田長政が関ケ原の合戦で東軍の武将として大活躍する一方、自身も九州の西軍勢力を次々と攻略し、真意はさておき徳川家康の天下取りに貢献することに。
お城造りの実績として、豊臣大坂城(1583年|豊臣秀吉の下で縄張り等を担当)、中津城(1588年|新築)、広島城(1589年|毛利輝元の依頼で縄張りに関与)、名護屋城(1592年|豊臣秀吉の下で縄張りを担当)、福岡城(1601年|黒田長政と共に新築)などがあります。
加藤清正(1562~1611)

石垣積みのスペシャリストといえばこの人ですね。
尾張生まれ。豊臣秀吉子飼いの武将で、織田信長の後継者を巡り秀吉と柴田勝家が争った賤ケ岳の戦いで大活躍、七本槍のひとりとして称えられます。 その後も秀吉の天下統一に尽力し、九州平定後には肥後国の北半分を拝領、朝鮮出兵にも参加します。 秀吉の死後は徳川家康に接近し、関ケ原の合戦時は九州の西軍勢力を次々と撃破、その功で肥後国の南半分も獲得します。 しかし恩義のある豊臣家と徳川家との対立には苦悩していたようです。
お城造りの実績として、熊本城(1601年|中世の城があった場所に新築)、名護屋城(1592年|豊臣秀吉の下で普請奉行)、蔚山倭城(1597年|朝鮮出兵時に縄張りを担当)、名古屋城(1610年|天下普請に参加)などがあります。
