
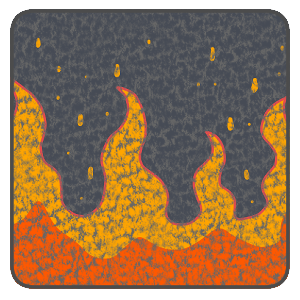
多くのお城が灰と化した3度の恐るべき災厄。お城もつらいよ受難物語
どうも! 当サイト管理人の犬彦です。
かつて何千何万とあったといわれている日本のお城の内、まともな形が残っているものはごく僅かです。その原因となったのが、お城のジェノサイドともいえる3度の災厄です。今回はその3度の災厄について解説します。
一国一城令

関ケ原の合戦(1600年)から大坂夏の陣(1615年)までは、まさに城郭建造ラッシュでした。 徳川家と豊臣家が並存する不安定な情勢の中で、いつ起こってもおかしくない戦乱に備えて、多くの大名が本城だけでなく支城もバンバン造りました。
大坂夏の陣で豊臣家が滅びると、徳川幕府はすぐに「お城は一国に一城しか認めない。支城は壊せ!」という命を大名に下しました。 とはいうものの、この命の基準は結構あやふやで、例外も多数ありました。 一大名に一城という方が近かったようです。 それでも国内の城郭の九割以上が破却されたといわれており、築城技術の進歩もここで途絶えてしまいました。
これにより大名が幕府や他の大名に対し戦争を起こすのが困難になったことはもちろんですが、領内の家臣が主君に楯突いて支城に立て籠ることもできなくなりました。 お城にとっては大災難だったこの命ですが、後の幕政だけでなく藩政の安定にもつながったわけです。
明治の廃城令

明治維新直後こそ領国のお城を引き続き維持していた大名家ですが、1871年(明治3年)の廃藩置県で華族となり、領国のお城を離れて東京に移住していきました。 お城と大名家との関係が断絶してしまったわけです。
1873年(明治6年)、いわゆる「廃城令」として知られる通達が、太政官(当時の政府にあった役職)から陸軍省と大蔵省(今の財務省のようなもの)に発せられました。 これにより、300以上あった城郭が、陸軍用地となるか(存城)、大蔵省によって売却されるか(廃城)に二分されました。
当時の政府にとって城郭はもはや旧時代の遺物、保存するつもりなどまったくありません。 存城となった43城でも、陸軍が邪魔と判断すれば、建造物も石垣も容赦なしに破壊されました。
また破壊を免れたとしても、ろくな管理もされず、荒れたまま放置され、その内多くの建造物が競売に掛けられました。 売却された建造物は、他の場所に移築されれば運が良い方で、大抵は解体され薪などにされました。
のちに有志の保存運動などによって命拾いした城郭はごく僅か。 天守に限ると、1929年の国宝保存法施行の時点で20棟しか残っていませんでした。
太平洋戦争

1941年に始まった太平洋戦争。 次第に日本が劣勢となり、末期になると国土が直接攻撃されるようになり、損害を受けた城郭も少なくありませんでした。
残存天守の内、水戸城、名古屋城、大垣城、和歌山城、岡山城、福山城が空襲で、広島城が原爆で失われました。 また仙台城では旧国宝に指定されていた大手門と脇櫓が空襲で焼失し、正殿と多くの城門が旧国宝だった首里城に至っては、沖縄戦により徹底的に破壊されてしまいました。
さて戦争で失われた天守の内、水戸城を除く6棟が再建されていますが、どれも鉄筋コンクリート造りです。 もちろん再建当時の建築法規では木造再建が難しかったというのもありますが、多くの地元民が二度と焼失しない丈夫な天守を望んだということも忘れてはいけません。





